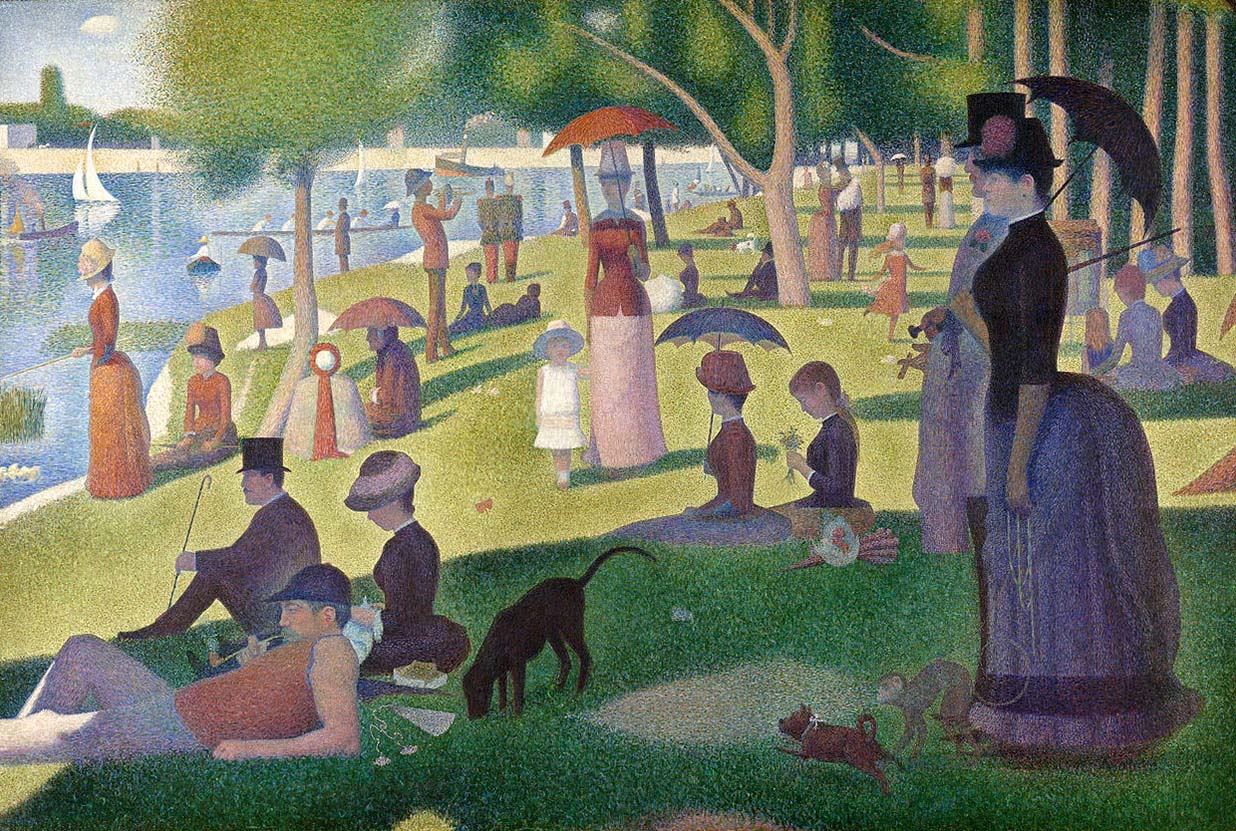尾州テキスタイル研修レポート」本科 西澤 彩希
9月19日、日本最大の毛織り物産地である尾州の織物について学ぶため、私たちは3ヶ所の施設を訪れました。
京都からバスに揺られて約2時間半、岐阜県羽島市にある『テキスタイルマテリアルセンター』に到着しました。
こちらの施設は、日本全国のファッション衣料用素材を集めた国内最大のテキスタイル資料館です。
出迎えてくれたのは大量の生地。素材を毎年追加しているとの事で、色とりどり、素材もさまざまな生地が部屋全体に並んでいました。実際に手に取り、触れながらデザイナーの方による素材講習を受けました。
まず、ファンシーツイードを中心に制作されている足立さんの講習を受けました。
たくさんの生地を用意して頂いた足立さんは、一つ一つ生地を見せてくれて、制作工程やその生地が出来るまでの流れを語って頂きました。制作に対する情熱が伝わってきて、その情熱がより良いもの作りへの活力になるのだと思いました。珍しい技法や素材を用いる事で、生地にさまざまな表情が生まれます。
足立さんは「普通の事では認められない。尾州の限界を考えて制作している」と仰っていました。
中でも印象に残っているものが左右の柄が違うジャケットです。隣り合う柄の中心に縫い合わせはなく、織り方を工夫して一枚の生地に柄が織られていました。今までの経験と技術、そして挑戦する心意気があったからこそ生み出された生地に触れられ、とても幸せで贅沢な時間を過ごせました。
「失敗した事を積み重ねて、どうやったらうまくやれるか考える」足立さんも過去にとんでもない失敗をしたと仰っていました。私は今までの織りの授業で、失敗ばかりしていると感じていました。糸が絡まったり、緯糸が飛んでいて何センチも前に戻ったりしていて時間に焦り、思い通りに進まない自分にもどかしさを感じていました。
そんな時に聞いた足立さんのこの言葉に私は励まされました。今までした失敗は今後の役に必ず活かせるだろうし、失敗しても挑戦する事が大切なんだと学びました。
続いて、ジャカード織物をメインに企画から販売まで幅広く活躍されている岩田さんの講習を受けました。
岩田さんには、染色された糸や、織物の設計図にあたる紋図などを見せていただきました。
それらの中に、たくさんの丸い穴が開いた厚紙がありました。これは、紋紙と呼ばれるジャカード織機に付属し、
その穴を読み取って柄を織る、言わば柄のデータです。複雑な模様になるほど紋紙の枚数は増えます。
岩田さんはこの紋紙を見ただけで、ある程度どのような柄が織られるかがわかるそうです。
今まで培ってきた豊富な知識を、足立さんや岩田さんは私たちにわかりやすいように教えてくださいました。
織物というのは、どの工程も緻密で繊細で、仕組みを理解するのは難しいですが、織りあがったものを見ると、
達成感や感動が生まれます。その分だけ根気や技術力が試されますが、二人の講義を受け、努力すれば素晴らしいものを生み出すことができるのだと痛感しました。
次に、愛知県一宮市にある「葛利毛織工場株式会社」さんへ見学に行きました。
こちらは主にメンズスーツ生地を制作されている工場です。懐かしさのある佇まいの工場は、昔から使われているションヘル織機のガシャンガシャンというリズミカルな音が響いていました。
ションヘル織機は人の手が加わります。私たちが普段学校で使う手織り織機同様、経糸・緯糸の準備、整経、綜絖通し、筬通しもすべて手作業で行われ、根気と熟練された技術を要します。
綜絖・筬通しの作業は大体6000本位の糸を通すのに3日はかかるらしく気の遠くなりそうな作業に圧倒されました。そして製織は1日に10mくらいしか織れないとのことです。
スピードと大量生産を重視される現代でなぜ時間と手間のかかるションヘル織機にこだわるのか、それは手織りの風合いを保つ為だそうです。ションヘル織機の特徴は、低速で織り進めるため、繊維を傷めることなく優しく丁寧に織られていきます。そのため手触りが柔らかくしなやかさある生地が出来上がるそうです。そうして作られたスーツに魅了され、芸能人や海外ブランドからオーダーされています。
工場を見学していて一番に感じたことは、従業員の方が織機と寄り添いながら作業をしていたことです。
一つ一つの作業を大切にされており、織りあがった後もミスがないか入念にチェックされています。
そうしたことが信頼につながり、世界進出できたり、価値があるものと認められるのだと思いました。
最後に伺ったのは岐阜県羽島市にある「三星染整株式会社」さんです。
繊維素材の染色・整理加工をしている工場での加工風景を見学させていただきました。取り扱っている繊維素材は幅広く、天然繊維から合成繊維まで加工を行っています。機械によるさまざまな加工技術を見せていただきました。加工されたものは最終的に検査が行われます。生地の幅、色、風合い、キズがないかなど、目視で検査されています。出荷後も何か不具合があった時などのために管理カードがあるとの事です。
生地はさまざまな工程を経て私たちの手元に届きます。
今まで当たり前のように生地に触れていた事が、実は多くの方が関わったからこそ出来たものだと学びました。
今回の見学で、テキスタイルの奥深さを知る事ができ、今後の制作の意欲を高める事ができました。


足立氏講義の様子 岩田氏講義の様子


葛利毛織工場株式会社

三星染整株式会社
「Made in Japanを支えること」本科 岡田 弥生
ここ10年ほど、日本の伝統工芸は世界で注目を集めつつあります。
第2次世界大戦に敗戦してから、日本人はアメリカやヨーロッパ各国に追いつこうと必死に努力をしてきました。
その結果、世界のどこにも負けないもの作りの文化が生み出され、一方で、日本の伝統文化は高齢化が進み後継者不足に頭を抱える時代を迎えました。
伝統を守り続けることは、新しいものを生み出し続けることでもあると学んだ尾州への研修。お話をしてくださった方々が、尾州でもの作りをしているということに誇りを感じている様子に大変刺激を受けました。
テキスタイルマテリアルセンターでは、お二人のデザイナーの方にお話を聞くことができました。ツイードを得意とされている足立さんのお話からは、新しいものを生み出し続けることの面白さと大変さを学びました。足立さんが生み出したテキスタイルはどれも斬新で、フィルムを織り込むような素材使いから、出来上がった布地からあえて糸を抜くなどの発想には伝統を超えたもの作りの面白さを感じました。続いてジャカード織を専門とされてる岩田さんのお話は、織機をいかに人が操るかで、織物に無限の可能性を見出すことができるように思えました。岩田さんに見せていただいた鳥模様の織物は一羽の中に様々な織り方がなされており、ただ色を変えたりするよりも味のある鳥が浮かび上がっていました。
お二人の話では、世界のファッションシーンを牽引するようなメゾンからもオーダーが来るということでした。
ファッションデザイナーとどのように仕事をするか。彼らの求めるものをどのように布に表現し、できないことははっきりと伝え、できることを最大限のものを作り上げるテキスタイルデザイナーという仕事についてもお話が伺え、貴重な経験となりました。
続いて、スーツ等を生産している葛利毛織の工場を見学させていただきました。現在では高速織機が普及し、大量の布地を短時間で織り上げることが当たり前となっている中、低速だからこそ手織りの風合いを残した布を織ることができるションヘル織機を昭和初期より使い続けられているそうです。そちらで織られたという布地は、確かに空気を含んだような柔らかさのあるものばかりでした。
最後に三星染整の整理加工工場を見学させていただきました。今まで、スクールでは織ることを中心に学びましたが、製品になるまでには織りあがったものにこんなにもたくさんの工程を経て加工を施さなければならないのかということに驚きました。何度もサンプルを作成し、その布地に最適な外観と触感を作り上げることは、きっと私が想像する以上に難しい作業だったと思います。
made in Japanの製品が世界で注目される今日、尾州で作られているような力強い日本の伝統を何らかの形で支える人材になりたいと強く感じました。