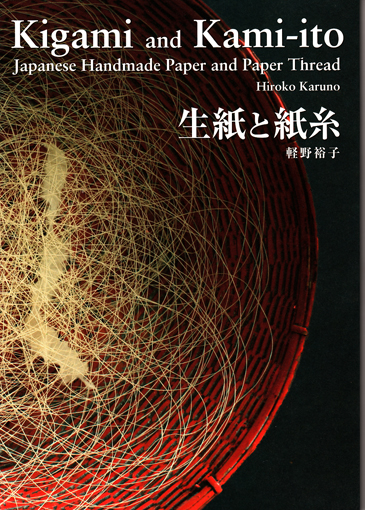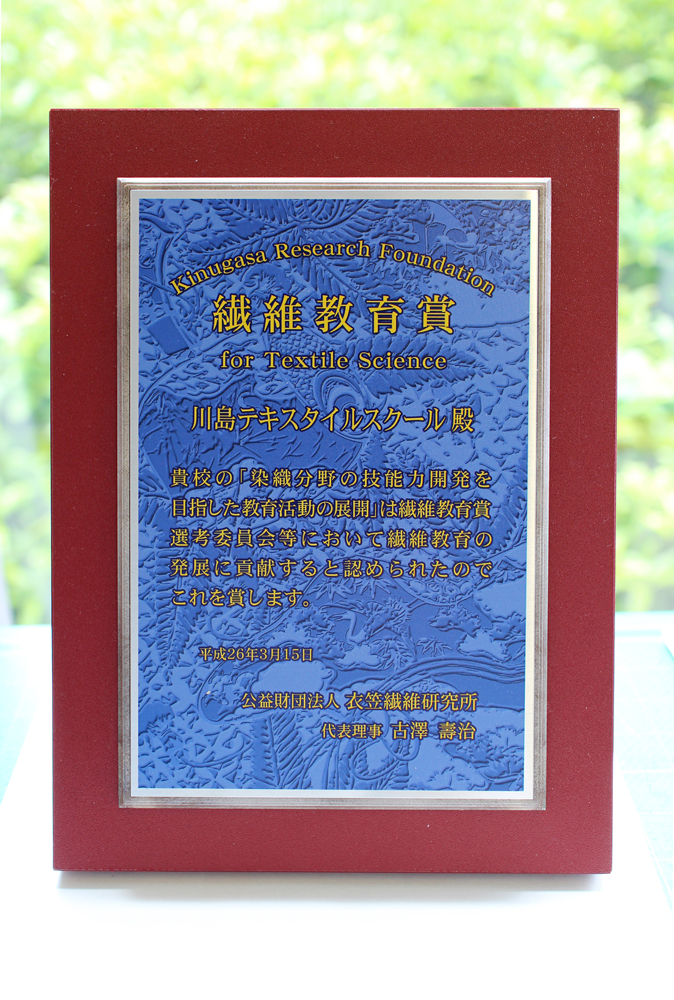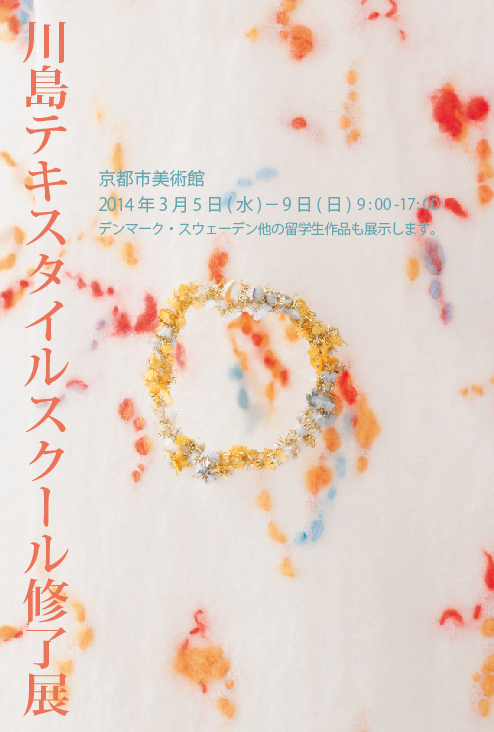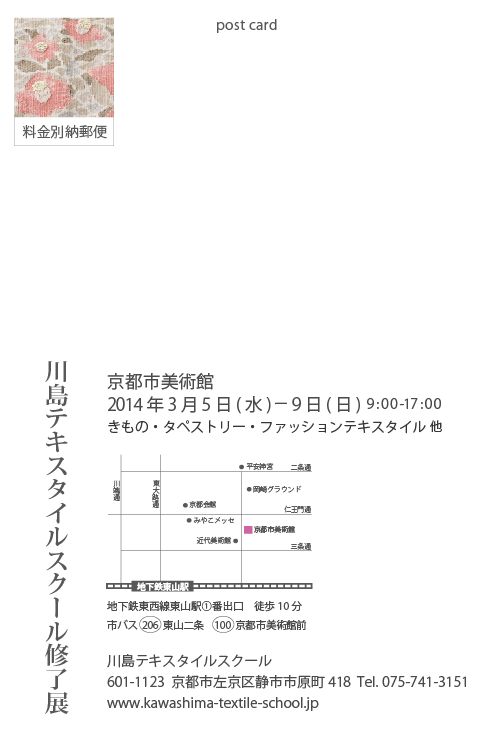スピニングの授業では、羊の毛を洗い、糸を紡ぐことを学びました。
写真は、羊から刈り取られたままの状態の毛です。
汚毛と言います。とっても動物の感じが伝わってくるもので、
この大量の汚毛を初めて見たときはびっくりしたのと同時に
これで作るのだと思うとワクワクしました。
まず、汚毛を洗うことからはじめました。
洗毛は毛質や汚れの程度で洗う方法を調整して少しずつ丁寧に
フェルトの様に固まらないように気をつけて洗っていきました。
出来上がった羊毛(原毛)を見て感動!真っ白でふわふわの原毛が出来上がりました。
さらに、ここから糸を紡ぎやすい様にいくつかの行程を経て原毛を整えていきます。
そして初めての糸紡ぎ、ウキウキしながらはじめたものの見るのとするのじゃ大違い。
細く均一に作ろうと思うほどに難しく、なんだかいびつなものがどんどん紡がれていきました。
しかし、先生の手や足の使い方をじっと見て、何度も回数を重ねていくうちにだんだんと
なんとか出来るようになりました。紡毛機で糸を紡いでいるときの
カタカタコトコトという音が心地よく教室中に広がっていました。
次はこの原毛を使い、冬にマフラーを織る予定です。どんなものが出来上がるのか次回の授業も楽しみです!!