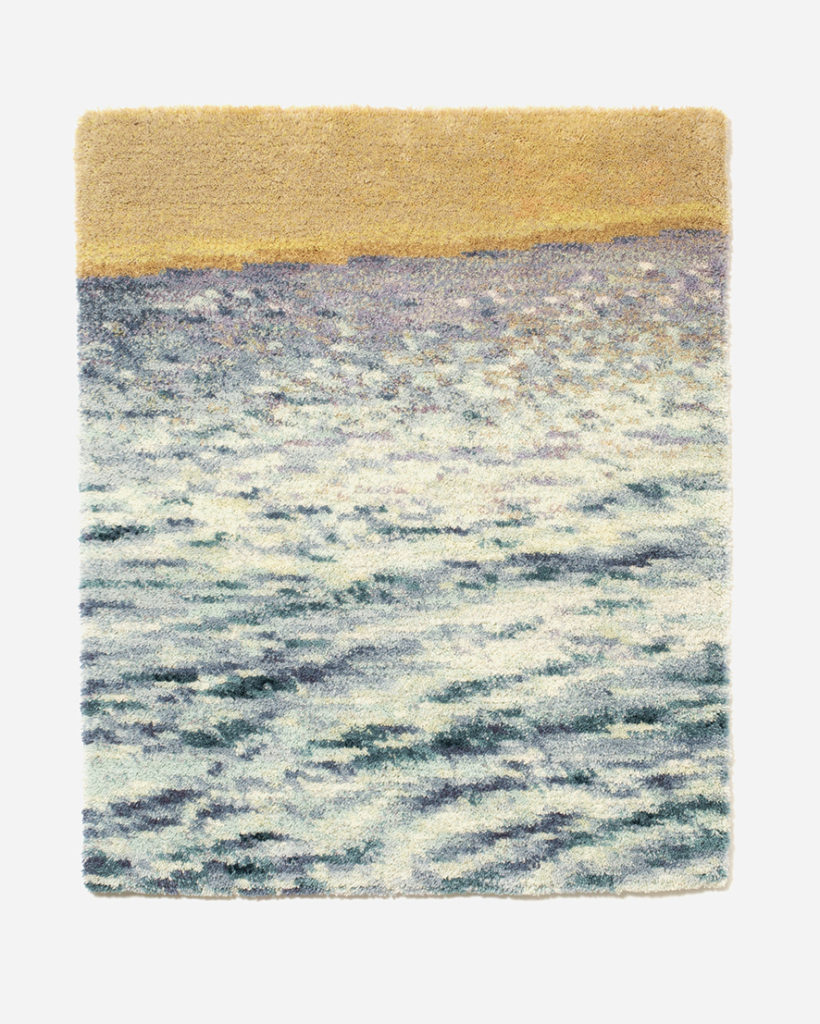川島テキスタイルスクール(KTS)を紹介するシリーズの国際編をお届けします。第3回は、海外からの留学生向けに初心者コースと絣コースを英語で教える表江麻講師のインタビューです。自身の海外経験、テキスタイルとの出会い、KTSで手織りや絣を教えることの思い、留学生との出会いから影響を受けたこと、スクールから見える国際性について語られた内容をお届けします。

◆ 暮らしが豊かになるものを作る
表講師は2009年にKTSを修了後、スクールのアシスタントに。同年、スクールが海外向けに「ビギナーズ」と「絣」を英語で教える「留学生コース」を設定したタイミングで、留学生の授業を山本講師と共に担い、国際コーディネートも担当することになりました。
自身も海外で暮らした経験が2度あります。最初は、子どもの頃にアメリカで。現地の公立の小学校に通っていた時、英語はアジア人である自分が周りと対等に交流するのに必要な手段だったそうです。次は、京都精華大学に在学中、交換留学でフィンランドへ。美術を幅広く学びたいと思い洋画を専攻し、留学先でやりたいことが少しずつ見えてきました。「テキスタイルを専攻している友人たちが、『使う』『着る』という明確な用途のあるものづくりをしていて制作に対するアプローチに魅力を感じたことと、明るいテキスタイルを室内に使って暗い冬を過ごすなど布が生活の中に溶け込んでいて、暮らしが豊かになるものを作るのが素敵だなと思ったんです」
日本が本場の技術を日本で学びたいと思い、大学卒業後にKTSへ。「年齢、国籍、経歴問わず、学びたい人に対してオープンなKTSがあったからこそ、好きな技術を身につけられました」。色の組み合わせと直線で考える、制約がある中でのものづくりが好き。作家活動で着物制作をし、スクールで海外からの学生に手織り技術を教える。いま、日本のことを世界に伝えるという、目指していたことが実現できている実感があるといいます。
◆ 世界中の織り手との出会い
母校が職場になり、主に海外から学びにくる人たちに教えて約10年。少人数制で、確かな技術を教えるスクールの方針に加えて、自身としては「学生にとっていい経験になるように」、「自国に帰ってからも一人で織れるように」心がけてきたそうです。「授業では、緯糸を織り込む角度や密度を安定させるなど美しく仕上げるコツを教えています。学んだことを帰国後に生かしてもらえたら嬉しいです」。
スクールから見える、世界の距離感があります。「織りをする人は、手仕事が好きで根気強い人が多いのではないかと思います。国や文化の違いがあっても、そうした技術との相性や、手織りに対する価値観の共有など、似たところがある人が集ってくる印象があります」。世界中の織り手との出会いが、教える喜びの一つ。その中で、自身の織りに対する思いに変化が生じます。
◆ 絣にとって何ができるか
変化のきっかけは、受講者から「歴史について聞かれることが多い」ことから。「留学生は、技術に加えて、昔は何の道具を使っていたのか、各地域の特徴など歴史的な背景の質問が多いです」。日本の手仕事、その伝統を作ってきた人たちに思いを馳せるようになり、「絣に対する思いが強まり、単に技術を教えるだけではなくなりました」。
そこで芽生えたのは、「技術を継承し、世界中に種まきをしている」という意識。「手織りは紀元前からつながっている歴史のある技術。(デジタル化が主流の)今の時代に、あえて手織りに特化したユニークな学校があり、47年続いていて、そこで学び働いている。時代が変わり消えてしまう技法がある中で、絣という手織りの技術をどうつなげていけるか。絣にとって私は何ができるか、役割を考えています」。
機が百台以上あり、染色室も整備され、織りも染めも専門の先生がいて、寮など設備が整うKTS。この規模で運営し続ける「手織りに特化したスクールがあるのはすごい」と留学生に言われることが多いそう。「海外でも大学のテキスタイル学科が閉鎖された話を聞きます。織りが好きな人が学びに来られる場として、KTSがこれからも息長く存続していけるよう力になりたい」と話します。
スクールをつづる:国際編2 「織りとの関わりの多様性」